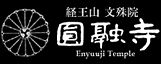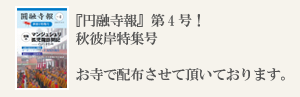死からはじまる世界
死は素晴らしい贈り物です。
なぜならば、あらゆる扉や窓を一斉に開け放してくれるからです。
死ぬことで、人間は壁の外側に出て行かざるを得なくなります
ディ―パック・チョプラ『ライフ・アフター・デス』
(住友進訳、サンガ、二〇〇八年)
死の世界はあるのか?
テレビの天気予報チャンネルを観ていると、
すっぽりと雲で覆われた日本列島の衛星写真が映し出されることがある。
その雲の下では、雨が降ったり、風が吹いたり、時には嵐のような大荒れの時もある。
私たちはその都度、天候に左右されて生きている。
ところが、当たり前のことだが、その雲の上では常に青空が広がり、さらにその空は宇宙へと続いている。
その雲の上と下と、一体どちらのほうが広いのかといえば、
当然、雲の上のほうがはるかに大きな世界が広がっているに決まっている。
私たちは宇宙のほんの片隅のちっぽけな空間で生きているにすぎないのだ。
それなのに、雲の下にいると、それだけが世界のすべてだと思い込み、
雲の上のことなどまるで気にかけることなく暮らしている。
もしかすると、私たちが生きているこの世界と死の世界というのも、
そんな雲の上と下のような関係なのかもしれない。
私たちは普段、日々の生活に精一杯で、死んだらどうなるのか、
死後の世界は存在するのかなどという問題について真剣に考えることはない。
いや、考えたところで確かな手がかりは何一つ見つからないだろう。
人類の長い歴史上、世界中のいたるところで、あらゆる宗教が死について、
または死後の世界について様々な教えを唱え、膨大な書物を残しているとはいえ、
それを信仰するかしないかは別にして、その真実は結局のところ自分が死んでみなければ確かめらない。
私たちは生きている限り、死を体験することはできないし、死が自己の消滅であるとするならば、
死を体験した者はもはや死を語る自己をもたない。死について、私たちは圧倒的に無知なのだ。
しかし、だからといって、死の世界が存在しないと果たして言い切れるだろうか。
それは雲の下にいる人間が雲の上に世界などないというのに等しいほど愚かしいことではないだろうか。
実は知らないだけで、生というちっぽけな世界より、死の世界はもっと広大なのかもしれないのだ。
死を生きる
私たちは生きているのか?
いま私たちは生の世界にいることを信じて疑わない。
しかし、突拍子もないことを言うようだが、
ひょっとすると私たちが住むこの世界だってすでに死の世界なのかもしれないのだ。
そんなことを考えたことがあるだろうか。
子どものころ、こんな思いに取りつかれたことがある。
もしかすると自分はもう死んでいて、こうして生きているつもりになっているけれども、
すべては幻なのではないかと。
家族みんなで幸せそうに食事をしていても、友だちと楽しく遊んでいても、
突然、「はい終了!」とばかりに目の前が真っ暗になり、
気がつけば自分もこの世界もすべてがまるで夢でも見ていたかのように存在していなかったなんて…。
そんなことを想像して、ゾっとしたことがある。
いま思えば子どもじみた荒唐無稽な空想ごとである。
しかし、大人になった今、自分は果たして生きているのだろうか、
目の前の世界は本当に存在しているのだろうか、と改めて考えてみると、納得のいく答えができるだろうか。
かのデカルトでさえ、自己という存在について長い思索の末にたどり着いた結論が「我思う、故に我あり」である。
自分がこうして存在している根拠は、自分が思うということでしか示すことができないのだ。
裏を返せば、「我思わなければ、我は存在しない」ということになるではないか。
また、英国のバードランド・ラッセルという哲学者が提示した「世界五分前仮説」というのがある。
私たちは、この世界がはるか悠久の昔から現在に至るまで存在し、
これからも続いていくと思っているが、もし五分前に全宇宙が誕生したと仮定した場合、
それに対して反駁できるか、というのである。
普通なら、「さっき昼ごはん食べたし」とか、昔の写真を取りだして、
「こんなかわいい時代があったのよ」などと説明するだろう。
しかし、過去の出来事も記憶も五分前に突然誕生したと言われれば、
それに反論することはできない。
それは五分前でなくても、一秒前、あるいは今この瞬間に誕生したと仮説を立てても同じことだろう。
私たちは過去に生きることはできない。
過去の出来事は文字通り過ぎ去って今はもう存在していないし、
いくら過去の記憶を呼び覚まそうとも、それを思い出しているのは今でしかない。
だとすると、これまで自分がどんな人生を送ってきたとしても、
この世界がどんな歴史を経てきたとしても、それが確かにあったと立証する術は何一つないということだ。
また一方で、これから先の将来についても同じように、
私たちの人生やこの世界が未来に存在すると誰がはっきりと言えるだろうか。
それどころか、今というこの時間さえも、思った瞬間から消え去ってゆく。
そう考えると、私たちは死の世界どころか、生の世界があるかどうかさえ分かっていないのである。
さて、私たちは生きているのだろうか?
死を生きる
普段、私たちは明日も当然生きていると思っている。
さっき「さよなら」といった友人には、いつかまた会えると思っている。
夜に「おやすみ」と声をかけた家族には、朝また「おはよう」とあいさつできると思っている。
それは生きていることを前提に暮らしているからだ。
でも、実はその保証は何一つない。
私たちは幻のような不確実な世界にかろうじて存在しているといってもよいだろう。
それならばいっそのこと、そもそも死んでいるのが前提だと考えたらどうだろう。
生きているのが当たり前なのではなく、本当は死んでいるはずなのに、こうして生きている、ということだ。
例えば、朝起きて「いま死んでいないから朝がある」、
朝ご飯を食べて「いま死んでないから空腹が満たされる」、
友人と会話をして「いま死んでないからこの人と会える」、
夜眠りにつく前に「いま死んでないから安心して休息できる」というように。
幻のようなこの世界で、平凡な人生かもしれないが、
こうして暮らし、食べ、働き、人と出会い、喜怒哀楽をもって誰かと気持ちを通わせることができるというのは、
それがどのような人生であれ、それだけで生きる全ての意味があり、まさに奇跡とも呼べるかもしれない。
『永遠の僕たち』(ガス・ヴァン・サント監督、二〇一一年公開)というアメリカ映画の中で、癌で余命いくばくもない少女が恋人に語るこんなセリフがある。
日が沈むと死ぬと思っている鳥がいるの。
だから朝になると目覚めた驚きで、美しい声で歌うんだって。
死んでない喜びで。
《「生」を生きている》という前提をひっくり返して、
《「死」を生きている》と思うと、逆説的ではあるが、
いのちの輝きをより一層感じられるような気がしてくる。
私たちもその気になれば、いつだって美しい歌声を奏でられるはずだ。
(②へつづく)

【『圓融寺小冊子』平成28年3月】
【不許無断転載】