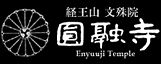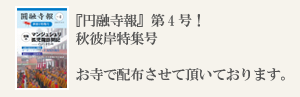いのちの呼吸
ひと生涯、ひと呼吸
いのちって一体何だろう?
それを私たちは生まれてから死ぬまでの間に存在する「何か」であると漠然と思っている。
しかし、いのちは実際に目には見えないから、それがどんな姿かたちをしているのか、
そもそも姿かたちがあるのかどうか知るよしもない。
また寿命というと、いのちの長さを指すことになるが、はたして本当に長さで測れるものなのだろうか?
『四十二章経』という経典にこんなお話がある。
ある時、お釈迦様が弟子たちに「人のいのちの長さはどれくらいか」と尋ねられた。
普通なら平均寿命から考えて「八〇年ちょっとかな」と思うかもしれない。
しかし、さすが修行を積んでいる弟子は違う。ある弟子は「ほんの数日です」と答えた。
あと数日で死ぬぐらいの覚悟で修行しています、という意味だ。
またある弟子は「食事の時間ぐらいです」と答えた。
今日この食事の後に死んでしまうとしたら、いかなる時も大切に思えるという心構えだ。
ところがお釈迦さまはその弟子たちに「お前たちはまだ仏道が分かっていない」と言った。
そして、最後にある弟子が「人のいのちはひと呼吸の中にあります」と答えたところ、
お釈迦さまは「よし!」と言って、そのお弟子さんを認めたそうだ。
私たちのいのちは、ハーと吐いてスーと吸う、その呼吸の中で生死を繰り返しているということだ。
生きている瞬間、瞬間が寿命だといってもよい。
まさに「ひと生涯、ひと呼吸」なのだ。
それなのに私たちはつい漫然と日々を暮らし、呼吸をしていることすら忘れてしまっている。
時には自分の人生を儚み、憂い、生きる力を失い、自ら自分の生涯を閉ざそうとする人さえもいる。
でも、人生のどんな境遇のいかなる瞬間であっても、呼吸と共にいのちが輝いているのだ。
アタマでは死にたいと思っても、いのちは生きたいと思っている。
にもかかわらず、それに気がつかずに、いのちをないがしろにしてしまってはもったいない。
第四夫人の正体は?
仏教学者のひろさちや氏が、ある本の中で『雑阿含経』という仏典に説かれるこんな寓話を紹介している。
一夫多妻制の時代の話だが、あるところに四人の妻を持つ男がいたそうだ。
男は第一夫人に対して一番の愛情を注ぎ、寝ても覚めてもいつもべったり一緒にいて、
お腹を空かせれば好きなものを食べさせ、暑さ寒さに応じて衣服を着させ、
何から何まで至れり尽くせりで、一度も争うことがなかった。
次いで第二夫人に対しては、第一夫人ほどではないにしても、とても仲良しで、
傍にいてくれると非常に喜び、いないときは不安でならなかった。
そして第三夫人に対しては、時々会うと心が和むが、ちょっとした諍いで一緒にいるのが窮屈になり、
かといってしばらく会わないと気になるような存在であった。
ところが第四夫人ともなると、彼女が一生懸命夫に尽くし、
どんな些細なことでも夫のすぐ傍らで常に気にかけていたにもかかわらず、
夫の方はまったく見向きもしなかった。
ある時、この男が遠い異国に旅立つことになった。
当然、妻たちもついて行ってくれると思っていたが、出発の際になると、
最も大事にしていた第一夫人は「私は一緒には行けません」とあっさりと断った。
第二夫人もまた同じように断った。
では第三夫人はどうかというと、
「お世話になったお礼に、国境まではご一緒しますが、あとはお一人でお出かけ下さい」とつれない返事であった。
予想外の返答に慌てた男は、そこでようやく傍らにずっといた第四夫人の存在に気がつき、
同行を求めると、迷うことなく頷いて一緒に異国に旅立った。
これはある譬え話だが、何を意味しているかお分かりだろうか。
もう少しじらしたいところだが、紙数がもったいないので早速答えよう。
異国への旅とは男の死を譬えている。
そして第一夫人は肉体、第二夫人は財産、第三夫人は家族、親せき、友人を意味しているのだ。
肉体も財産も親しかった人々も、
生前どんなに大切にしていたとしても死の旅にまでは連れて行くことはできない(なるほど!)。
とすると、第四夫人の正体は一体何だろうか。
経典によると「人の心」であると説かれているが、
それはちょっとしたことで一喜一憂するような不安定な心を指すのではなく、
いのちと捉えてみてはどうだろうか。
いのちはどんなときも私たちの傍にいて人生の支えとなり、死んだ後でさえも一緒にいてくれるというのに、
それを忘れて自分の肉体や財産、人間関係ばかり気にしているなんて、なんとも薄情なことではないか。
さあ、ここでちょっとひと呼吸して第四夫人を思い出してみようではないか。
波と海
人が自然に呼吸するリズムは一分間に平均約十八回といわれるが、
それは寄せては返す波のリズムと同じだという話を聞いたことがある。
確かに波と呼吸はとてもよく似ている。
波はまるで海が呼吸をしているかのごとく水面に浮かんだり消えたり生滅を繰り返す。
では、その波は一体どこから来て、どこに去って行くのだろうか?
波は波でありながらそのまま海なのだから、生じる波も、消える波も、それがいかなる変化を遂げようと、
海としてはずっと何も変わらない。
海はどこから来たわけでもないしどこへ行くわけでもない。
はじまりもなければ終わりもない。
私たちの呼吸が波のようなものなのであれば、いのちは海だといえる。
そうであれば、呼吸をしているのは誰なのだろう。
この私が呼吸をしているのではなく、いのちが私を通じて呼吸をしている、そう考えられないだろうか。
私たちは何の因果かこの世に生まれ、いのちという大海の上で幾度となく呼吸を重ねて、
そしていつかは消えゆく存在である。
しかし、波が消えても海がなくならないのと同じように、人生が終わりを迎え、
最後の息を引き取ったとしても、いのちそのものは消えることはないように思えるのである。
また、海面の波はそれぞれ大きさも形も違うし、持続する時間の長さも異なるように、
個としての私たちの人生もそれぞれ人によって違っている。
しかし、そこに存在の本質があるわけではない。
水面では一つひとつバラバラの波のような存在でも、その根っこは同じいのちということになるだろう。
どんな波も大きな海へと帰っていくように、私たちもまた、それがどんな生き方であれ、
最後はみな大きないのちに戻っていくのではないだろうか。
そう考えると、私たちは生と死について大きな誤解をしているのかもしれない。
生と死は対立的なもので、その間に決して乗り超えることのできぬ壁があるというのが常識的な捉え方だ。
生の世界と死の世界は二つの全く別の世界であり、生者は死者と決して出会えないと思っている。
しかし、波と海は、一体どこからどこまでが波で、どこからどこまでが海だというのだろうか。
そこには境界線というものはない。
だとすれば、生と死もまた、その間を分ける境界などそもそもないのではないか。
『般若心経』に「不生不滅」(ふしょうふめつ)という一句があるが、
それは始まりも終わりもなく、生じることも滅することもないいのちの姿を表現した言葉だろう。
だとすれば、本当の死というのは、「生」や「死」という概念の消滅を意味するだけなのであって、
それはいのちの消滅を意味しない。そういう意味では、誰も死なないと言えるのではないだろうか。
また、水面の波の世界だけをみれば、
人生はまさに「会者定離」(えしゃじょうり:出会ったものとは必ず別れがあるという理)という言葉通りだが、
いのちの海の中では、あらゆる存在が出会いも別れもなく、生も死も超えて、ずっと永遠に共にあるのだ。
そういう世界を「俱会一処」(くえいっしょ)というのだろう。
生の世界と死の世界は二元的なものではなく、つねに「いま、ここ」にあるのだ。
とんちで有名な一休禅師が死の際に歌ったとされる一句がある。
死にはせぬ どこへも行かぬ ここに居る たづねはするな ものは云わぬぞ
極楽浄土はどこにある?
輪廻の世界
輪廻って一体何だろう?
仏教では輪廻の世界を六つに分けて、
地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天の六道(「道」とは世界という意味)という。
なんだか子供だましにも聞こえるし、
今どきの小学生に「嘘をついたら地獄に堕ちて閻魔様に舌を抜かれるよ」などといっても誰も信じないだろう。
輪廻の世界なんか存在しないといったらそれまでだ。
しかし、波と海の譬えのように、輪廻とは、海上に繰り返し浮いては消える波のようなものだと捉えたらどうだろう。
波は波として確かに存在はしているが、それは何らかの条件が合わさって海の上に起きた現象に過ぎず、
波という独立した存在があるわけではない。
水面では別個の波も、海からすれば波はすべて同じ海だ。
これと同様に、輪廻の世界も大きな一つのいのちの表層に仮に生じた現象であり、
様々な世界や個々の人生があるようにみえて、実は同じいのちの表現でしかないと言えないか。
そうであれば、輪廻の世界はあるとも言えないし、ないとも言えない幻のような存在だ。
その世界で生きる個々の人生も、その人生を生きる私という存在もまた、あるとも言えないし、ないとも言えない。
いのちが仮に私という存在として生きているといったところか。
仏教的に解釈すれば、本来は「無我」なる状態がこの世界の真実のすがたであり、
それを海に譬えることができる。
そして、その水面に隆起する波は、そのまま海そのものであるのに、
それを海と分離して実体視してしまう意識が「我」ということになる。
その「我」が地獄、餓鬼、畜生、人などの世界をつくりだし、
その中で「私の人生」という幻想の物語が展開しているといえる。
また、波はつねに変化し、一時も立ち止まることがないように、
私たちの人生は苦楽あいまじわり、天にも昇った心地であったのが、
突如として地獄のような苦しみの境地に突き落とされることもあるし、
またその逆に苦しい地獄から解放されることもある。
ただ、その変化を自分の思いのままに操ることはできない。
そのような人生を仏教では「諸行無常」(あらゆる物事、現象は変化してやむことがないという理)、
「一切皆苦」(すべてのことは思い通りにならない)と言い表す。
私たちはそんなままならない人生を嘆き悲しむかもしれない。
しかし人生の波がどんなに荒れ狂うことがあっても、不本意な姿かたちになろうとも、
私たちの本質であるいのちの海は何一つ変わらず穏やかなままである。
そこにこそ「涅槃寂静」(ねはんじゃくじょう)という悟りの世界があるのだろう。
悟りの世界というと、それを私たちは遥か彼方のまったく手の届かない別に次元にあるものだと思ってしまうが、
波はそのままで海なのだから、
私たちの住む世界が地獄であろうと何であろうと、私たちはどこにも行く必要はない。
いつでも同じ大きないのちの中にいて、自分のいるその場所がそのまま悟りの世界であるはずだ。
こんなふうに輪廻の世界を考えてみると、
私たちが今生きている世界や自分の置かれた境遇や人生が少しは違った目でみることができないだろうか。
いま抱えている悩みや苦しみも一瞬にして消えてなくなりそうだ。
「えっ、なくならない!?」
確かにそうだ。
この世界も人生も夢のような幻想だとか、本質は同じいのちだとか言われても、
苦しみの真っ只中にいる人にとっては何の気休めにもならないだろう。
どんな悪夢も現実ではないとしても、夢の中では苦しいものは苦しい。
目覚めない限りは、あいかわらず輪廻の荒波にもまれ、必死にもがくことだろう。
それが輪廻の世界の非情さだろうか。
極楽浄土はどこにある?
仏教では、輪廻の世界で苦しんでいる人々を救うために阿弥陀様がつくった極楽浄土があるという。
そこにたどり着いたものは、輪廻の束縛から解き放たれ、誰もが仏になることが確定されているそうだ。
「阿弥陀」というのは漢訳すれば「無量寿」といい、不生不滅の永遠のいのちということだ。
私たちも阿弥陀様のもとに行けば、自分が永遠のいのちであることに気がつくことができるのだろうか。
その極楽浄土は西の最果てにあると言われているが、
この輪廻の荒波のはるか向こうにぽっかり浮いている島なのか、大陸なのか。
生きているうちには無理そうだが、せめて来世では行きたいものだ。
そう願う人々によって形成されたのが浄土教である。
極楽浄土の浜辺から、これまで幾度となく乗り越えた波を眺めれば、全てが美しい海の風景だと思えるだろうか。
しかし、そんな安息の場にどうやったら行けるのか?
何度輪廻を繰り返してもたどり着けないのではないかと思うだろうが、浄土教の教えでは、
それが意外と簡単で、「南無阿弥陀仏」とわずか十遍ほど唱えるだけでもいいという。
「南無」とは平たく言えば「あなたにお任せします」という意味なので、
阿弥陀様に全部をお任せしますということだ。
確かに潮の流れも波の力も自分でコントロールするのは到底不可能なことで、
力尽きて溺れるのが関の山だろう。だったら、流れに身をまかせているしかないではないか。
流れの行く末が不安かもしれないし、いつか煩悩の重さで海の底に沈んでしまうのではと心配に思うかもしれない。
しかし浄土教を広めた恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)は『往生要集』(おうじょうようしゅう)の中で、
小石は水の上に置けば沈むが、船に乗せれば沈まないように、煩悩の石をいくつも背負って生きている私たちも、
そのまま阿弥陀様の船で浄土まで連れて行って下さるのだと言っている。
私たちはもうすでに阿弥陀様の船に乗っているのだから、
この身についてあれやこれやとぼやかずに、あとは船長さんにお任せしましょうということだ。
さらに私の薄っぺらなイメージで恐縮だが、浄土の浜辺はそのまま海の底へとつながり、
私たちの足元まで続いているはずではないか。
だとすれば、大海のどこにいようと私たちの足元には必ず浄土がある。
ここが浄土だと思えば浄土ではないか。
そんなこといくら語っても結局はファンタジーだと言うかもしれない。
まさにその通りで、極楽も地獄もファンタジーでしかないと思う。
でも、私たちがこうして生きて現実だと思っているこの世界だって同じくファンタジーじゃなかろうか。
どのみち、あるのは大きなひとつのいのちだけ。
そのいのちが様々なファンタジーの世界でそれぞれの物語を綴って生きている。
だとしたら、私たちのこの狭い世界だけでなく、視野を広げてもっと大きな世界を想像してみたらどうだろう。
そうすれば、この輪廻の荒波も少しは気持ちのゆとりをもって乗り越えられそうだ。
完


【『圓融寺小冊子』平成28年3月】
【不許無断転載】